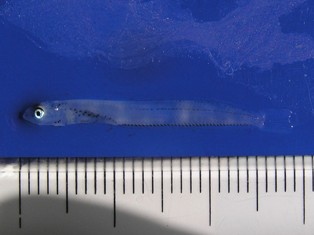小さな魚達の大きな幼稚園〜宮古湾周辺で育つ稚魚達の紹介〜(その2:非食用)
写真その1(漁業対象)・ 写真その2(非漁業対象)・
写真その3(大きくならず,一生を藻場・干潟で過ごす魚)
宮古湾奥部の藻場・干潟は重要な稚魚の育成場。
大きな魚はいなくても、大きく育つ稚魚たちがひっそりと、逞しく生きています。
大きくなると80cmを超えるヒラメも、生まれた時はたったの3mm。
三陸の海で生きる、小さな魚達の大きな幼稚園。
その幼稚園の生徒達を、稚魚調査の記録から少しだけ紹介します。
アナハゼの1種 Psudoblennius sp.
左:全長約25mm 2007年4月9日撮影
右:全長約25mm 2007年4月9日撮影
岸壁で釣りをしてると,外道として釣れることがあるアナハゼ。
宮古湾の藻場にも生息している。
似たような種類が多い。
クマガイウオ属の1種 Agonomalus sp.
左:全長約12mm 2007年4月12日撮影
右:全長約12mm 2007年4月12日撮影
成魚は体が硬く,ヨロイを身にまとったような形をしている。
クマガイウオとアツモリウオがいるが,仔魚の段階での見分けは難しい。
チシマトクビレ Agonomalus sp.
全長約25mm 2008年4月13日撮影
その名の通り,北海道などで分布が確認されている。
しかし,宮古湾でも,稚魚調査で生息が確認された。
トクビレ(ハッカク)の仲間だが,あまり大きくならない。
ガジの一種 Ernogrammus sp.
全長約30mm 2007年2月26日撮影
宮古では「かたなぎ」と呼ばれることもある。
食用とはならない。
ギンポの1種 Enedrias sp.
左:全長約30mm 2007年3月19日撮影
右:全長約30mm 2007年4月7日撮影
ガジ同様,宮古では「かたなぎ」と呼ばれる。
食用とする地域もあるが,宮古ではほとんど食用とされない。
アミメハギ Rudarius ercodes
全長約30mm 2008年2月25日撮影
カワハギの仲間で,宮古湾では藻場に生息している。
あまり大きくならないので,食用とされない。
フグの1種 Takifugu sp.
左:全長約40mm 2007年2月28日撮影
右:全長約50mm 2007年4月15日撮影
食用となるフグの種類は限られているが,小さいサイズでは種類がわかりにくいこともある。
このサイズでも膨らむことが出来る。また,既に毒を持つ。
写真その1(漁業対象)・ 写真その2(非漁業対象)・
写真その3(大きくならず,一生を藻場・干潟で過ごす魚)